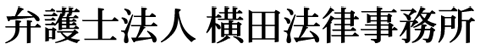Column
- 2019/02/25 アクセス・お問合せ ページを更新致しました
- 駐車場の場所入りの地図を掲載しました。
- 2017/08/29 平成29年民法改正 1
-
【平成29年民法改正 1】
民法債権法改正が本年、ようやく通りました。
影響のない分野を探す方がきわめて困難な大改正です。不動産取引に関しても大きく変わりますが、今回は賃借人の保証について。
個人根保証が民法465条の2以下で制度化されていますが、さらに改正されます。
極度額の約定が効力要件とされ、継続的保証の上限が画されます。
465条の3では、元本確定期日について5年超は無効、定めなきときは3年となります。もっとも、運用を見ないと行方のわからないこともあります。
賃借人の自殺は、賃料の下落をもたらします。
465条の4第1項では、主債務者の死亡が元本確定事由となります。
それでは保証人は、賃料下落について損害賠償責任を負うことになるのか、元本確定の結果、損害賠償責任を負わないのか。責任を負わない、という見解もあり得ます。
しかし、別の見解として自殺の着手自体は生前にあるので、その生前の賃借人の用法違反の行為の責任に含まれる、したがって責任を負うという見方も有力です。かくも不幸な限界事例はありますが、全般としては過酷に過ぎるといわれた賃借人の保証や、被用者の身元保証に、明文の責任制限が設けられることは、社会全体の進歩のためにやはり民法債権法改正は必要だったのだと思えてきます。
- 2016/04/01 ソフトウェア開発契約における契約の成立過程について
-
「契約とは、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である。」と民法の最初の最初で学ぶし、それが口頭での合致で足り、契約書は有力な証拠であっても、契約の成立の一徴表に止まる位置づけであると大学では学ぶ。
それが司法研修所で事実認定の仕方を学ぶ内に,民事訴訟法228条4項「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」、すなわち、(1)署名や印影が本人のものであると、本人が自分の意思で署名し、押印したことが事実上推定され、(2)本人の意思に基づき署名、押印されたものがあれば、それは文書の作成者の意思に基づき作成されたという書面の真正が推定される、という、いわゆる二段の推定をたたき込まれる。こうして、物の売買やお金の貸し借りなどの契約をめぐる紛争で、署名と印影のある書証を中心に立証を組み立てるので、法律家も契約書をもって、契約の成立時期と錯覚するようになる。
ところが、ITの発達に関連した紛争が少なからず持ち込まれるようになり、契約書の成立時期をもってしてのみで合意の形成時期が明らかにならない紛争類型として、ソフトウェア開発契約にまつわるものが多く見られるようになった。
問題の所在であるが、ユーザー企業がITにより実現したい事業あるいは業務が何かについて、そのユーザー企業が当初から開発内容を明確にイメージした上でソフトウェア・ベンダー企業に具体的な開発内容を明示して依頼するという例は多くなく、むしろある事業についてシステム化の導入で効率化を図りたいという漠とした要望について、まずベンダーからの提案を受け、打合せを重ねていく中でイメージをすりあわせ、システムの内容を明確化していくことが多い。確かに請負契約の一種というべきソフトウェア開発契約の締結時にシステムの仕様が具体的内容まで確定していることはほとんどない。
加えて建築請負の場合には建築確認制度など設計図書の事前提出を要求されるので、合意形成の時期が判明するが、そのような節目となる手続がない。さらに、発注するユーザー企業側が急ぐ原因はすでに述べたが、経済的基盤の弱いソフトウェア・ベンダー企業も受注を急ぐあまり、システムの仕様が最初から確定しない。そして、開発側と発注側とでの情報格差とこれに由来するコミュニケーションギャップの問題が尚更話を複雑にする。

ともあれ、明示の合意に至るまでには、要件定義書と基本設計書を取り交わす段階にまで至らなければならないようであるが、建物の引渡し相当する、検収の段階を過ぎても、バグはつきものとされ、結局は瑕疵担保責任の有無についての判断において契約書外の合意形成の諸要素を判断せざるを得ない。
この点、東京地方裁判所平成9年2月18日判決(判例タイムズ964号172頁)は、運送業における運送管理システムの「瑕疵」につき、以下のとおり述べる。
コンピューターソフトのプログラムには右のとおりバグが存在することがありうるものであるから、コンピューターシステムの構築後検収を終え、本稼働体勢後となった後に、プログラムにいわゆるバグがあることが発見された場合においても、プログラム納入後、遅滞なく補修を終え、又はユーザーと協議の上相当と認める代替措置を講じたときは、右バグの存在をもってプログラムの欠陥(瑕疵)と評価することはできないものというべきである。
この手の類型に得意な弁護士になるためには、事件を持ち込まれた時に臆することなくチャレンジするしかないのだろうが、現状は逃げてもいない代わりに悪戦苦闘が続いており、「ITはご専門ですか」という答えに窮する質問が来たとき、戦果が出たら差し障りのない範囲でコラムにしたいなとは思っているが、目下「弁護士は専門を掲げてはいけないんです」と答えることにしている。
- 2016/01/08 犯罪収益等移転防止法と本人確認についての随想
-
所得税の申告の準備もそろそろ必要なので、通帳を順番にチェックし、最後に経費をざっと計算するため、弁護士会会費納入用の自分の通帳をチェックしてていた。
私の単名ではなく、事務所の名前が先に入っている。
この通帳を作った2002年に、国際的な犯罪の防止にかかる条約の要請と、国内における詐欺犯罪の防止の要請の趣旨で本人確認法ができたことを思い出す。ただ本人確認法のころは法律家は規制の対象外だったので、私が弁護士登録をした当時は、さほど手続的に困難なくこの口座を作ることができた覚えだった。
しかしマネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)が2003年に、対象事業者を拡大し、金融機関だけでなく、職業的専門家を広く含め、その中に法律家も含めるよう勧告があった。本人確認法は2008年3月1日、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益等移転防止法と略)の全面施行に伴い廃止された。
犯罪収益等移転防止法は、事業者が依頼者の「疑わしい取引」を発見したとき所定の行政庁への届出を義務づけるものだが、弁護士業においては、弁護士の守秘義務、ひいてはそもそも弁護士としての職務の本質を損なう緊張関係をはらむため、犯罪収益等移転防止法第11条により本人特定事項の確認等については日弁連の会則(依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程)で独自に規律することで決着がついた。
ともかく、単なる本人名義でなく、団体の役職や肩書きなどの入った通帳を作るのは年々難しくなったことは変わりがない。
他方でヤミ金口座の閉鎖は度々相談を受け、経験もしたし、本人確認の強化に関連して発生する事件も経験した。以上のとおり自分の弁護士としての歩みと本人確認の強化と時期がシンクロしているため、何かと興味をもって本人確認法(廃止)、犯罪収益等移転防止法の改正と運用を眺めてきていたが、インターネットの質問サイトに次のようなものがあった。
内容は、質問者が退職した際、旧勤務先より、「○○社○○長 質問者氏名」の通帳を受け取ったとのこと。質問者が在職中開設したものだが、退職後質問者が自身の免許証と通帳で解約できるか、との問い。なお目的はお茶代などを管理する目的だったので わざわざ肩書き付きにしたとのこと。
これに対するベストアンサーは「まさに私もそういうことをしています。自信はないのですが、私の場合は・・・、通帳自体は、名称は『なんとか会』と出来ますが、登録は個人名としなければならない様です。ですから、その通帳は質問者さんの名義の通帳と考えてよいと思います。」というものであった。
回答日時が「2004/12/28」とのことで、緩い時代だったのだろうという感想。この問いで法律相談を受けた場合、もう少し銀行に提出した書類など詳しく聞きたい。そういえば冒頭の普通預金口座を作るにあたって、弁護士会の指導を必ずしも理解しきれないまま作ったが、その経過を後日省みるに、銀行に対し任意団体として当事務所を届けていた。私個人の収入とも預り金通帳とも完全に峻別された、事務所資金通帳が存在していることになる。(横田 亮)
- 2015/09/01 ホームページ開設にあたって
-
この度、横田法律事務所のホームページを開設致しました。
このホームページを媒介にして人の輪が拡がっていき、職業人として関わった皆様に奉仕することを心より願っております。
ホームページ立ち上げにあたっては、職業人としてのこれまでの自らの歩みの再点検をすることになりました。誠実に自らを省みた内容になっていると思っておりますが、ご意見頂ければ幸甚です。
また、当事務所がいつまでも「値札のない寿司屋」のごとくあり続けるのも良くないため、日弁連の報酬に関する規程に沿った形で当事務所の報酬規程をホームページ上でも開示させていただきます。
ホームページの開設は、思いがけず随分と責任の伴う作業でした。今後より一層、衿を正し自己研鑽に務めていく所存です。